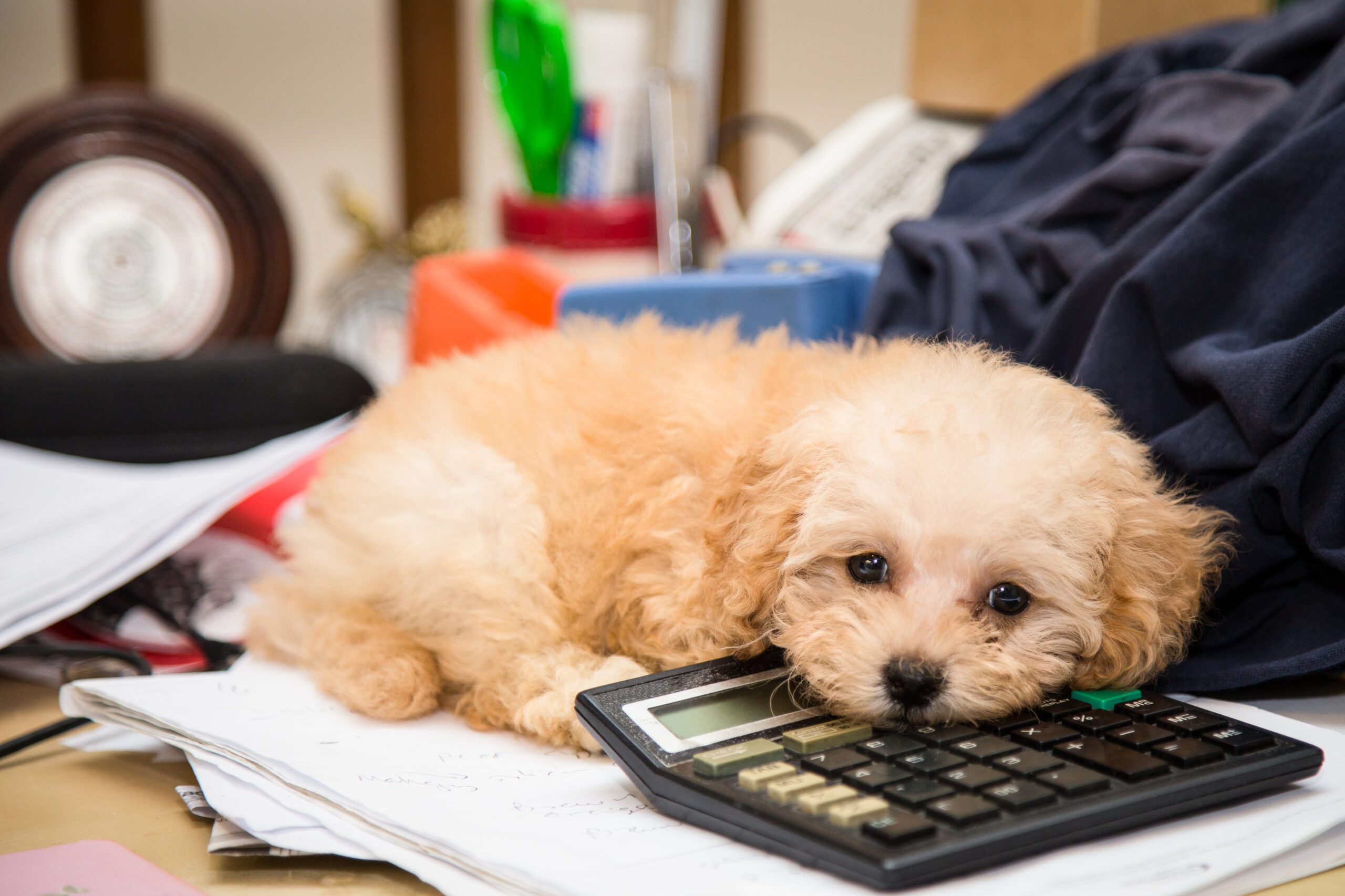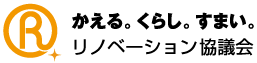マンションを購入時にチェックすべき5つのポイント!

マンションを購入する際は、価格や間取り以外にもチェックした方が良いポイントが様々あります。
基本的には、一度、マンションを購入すると長く住み続けるため、 周辺環境や災害リスクも重要になるからです。また、購入する前に資金計画をしっかりと立てておくことも重要です。
この記事では、マンションを購入する際のチェックポイントを紹介します。ぜひ参考にしてください。
もくじ
マンションを選ぶ際にチェックすべき5つのポイント

マンションを選ぶ際には、チェックすべきことがあります。この記事では、大きく下記の5つに分けてどんなポイントをチェックすべきかを紹介します。
マンションを選ぶ際のチェックポイント
- 災害リスクや周辺環境をチェック
- 資金計画や予算をチェック
- 不動産業者をチェック
- 物件の性能をチェック
- 内覧の際のチェックポイント
詳しくみていきましょう。
1.災害リスクや周辺環境をチェック
マンションを購入するということは、そのマンションに長く住むということです。
そのため、周辺の環境や安全性は非常に重要です。
まずは、災害リスクや周辺環境をチェックしていきましょう。
地域
まず、通勤や通学を考慮して候補地を選びます。毎日のことなので、できるだけアクセスの良いエリアが望ましいでしょう。最寄り駅からの距離だけでなく、電車やバスの便数も重要です。
次に、実家からの距離も考慮しておくことをおすすめします。特に子育て世代は、両親の近くに住むことで育児や介護の面で助かることが多くなります。実家が他県にある場合は、新幹線の駅や空港までのアクセスも検討に入れておくと良いでしょう。
最終的には、自分たちの生活に合った地域を見つけるために、実際に現地を訪れてみることもおすすめします。
環境や利便性
通勤・通学などのアクセス面からいくつかの地域が候補として上がったら、それらの地域の生活環境をチェックしてみましょう。
買い物施設や医療施設の充実度、学校の評判や習い事などの教育環境などが理想とするライフスタイルに合っているかを見定めます。
子育て中の場合、学校が近いと安全面でも安心ですし、両親が近くに住むことで育児のサポートが受けやすくなることもあるでしょう。
また、駅近の物件は便利で人気がありますが、商業施設が多く混雑したり騒音が大きいというデメリットもあります。
一方、駅から離れた場所は静かで自然が豊かな地域も多く、子育て環境としても魅力的な街が多くなります。例えば駅から徒歩15分以内やバスでのアクセスが許容範囲かどうかなどを決めておくと、物件選びがスムーズになります。
地域を広めに設定したり、いくつか候補をあげておくことも大切です。特定エリアに絞ってしまうと物件数が限られてしまいますが、広範囲で探すことで選択肢が増え、理想の物件に出会える可能性が高まります。
災害リスク・ハザードについて
災害リスクを考慮する際は、まず海抜や河川、山などの地形に近いかどうかを確認しましょう。海抜が低い地域は地震や台風の際に津波や高潮の被害に遭いやすくなりますし、山に近い地域は土砂災害のリスクが高くなります。
さらに、自治体が発行しているハザードマップを活用することも重要です。ハザードマップには、地震や大雨の際の被害リスクが細かく表示されており、土砂災害の危険箇所や避難ルートなども確認することができます。
ハザードマップを事前に確認しておけば、災害リスクを最小限に抑えた安全な地域を選ぶことができます。
2.資金計画や予算をチェック

資金計画が曖昧なまま物件探しをしていると、最終段階になって資金が足りずに困ってしまう可能性もあります。そうならないためにも、初期段階でしっかりと計画を立てておくことが重要です。
ここでは、資金計画に関する下記の5つの項目について解説します。
- まずは予算の把握から
- 手付金や申込金は現金で。いくらか頭金が必要
- 住宅ローンについて
- マンション購入時の諸費用
- 購入後にかかる費用
では、早速確認していきましょう。
まずは予算の把握から
「今の家賃と同じ支払いで借りられる金額+今の貯金額=購入する物件の予算」という単純計算をしてしまう方がいますが、これはとても危険です。
不動産の購入には、物件価格に加えて保険や手数料などの諸費用がかかります。さらに、リノベーションをする場合はその費用も発生します。
物件の購入にかかる費用は「物件価格+諸費用(+リノベーション費用)」です。
そのための資金は「手持ち資金+住宅ローンで無理なく返済できる借入額」で支払います。
また、建物は時間が経てば劣化するため、子供の進学などライフイベント関連の出費に加えて将来的な修繕にも対応しなければなりません。
これらの費用を総合的に考慮し、手持ち資金と住宅ローンを合わせて無理なく返済できる資金計画を立てることが重要です。
まずは不動産のプロに相談し、具体的な予算や必要な費用を確認しましょう。
手付金や仲介手数料は現金で。いくらか頭金が必要
住宅のチラシや金融機関のパンフレットなどに「フルローン」という言葉が書かれていることがありますが、これはあくまで「物件価格の100%のローン」という意味です。
売買契約時に支払う手付金や仲介手数料は現金で支払う必要があるため、物件購入にかかる資金を全額をローンで賄うことはできません。諸費用も住宅ローンと合わせて借りられる場合もありますが、融資が実行されるのは引き渡し時となるため、運転資金としてある程度の現金を用意しておく必要があります。
手付金の金額は物件価格の1割、契約時に支払う仲介手数料は半額が不動産取引の慣例となっているため、想定する物件価格の10〜15%の現金を用意しておくと良いでしょう
住宅ローンについて
住宅ローンの金利には、変動金利と固定金利の2種類があります。
一般的に変動金利の方が金利は安くなりますが、将来的に金利が上昇するリスクがあります。一方、フラット35などの固定金利型ローンは、35年間金利が変わらないため、返済額も変わらない安心感があります。
どちらも、年齢や収入、ライフプランに応じて決めることが重要です。
住宅ローンの審査基準は金融機関によって変わりますが、月々の返済額から逆算して自分がいくら借りられるか、プロに相談するのが賢明です。
また、リフォームローンも利用できるので、リノベーションを考えている場合はこのオプションも検討すると良いでしょう。これらの情報を総合的に判断し、無理のない資金計画を立てることが、安心して住宅を購入するための鍵となります。
住宅ローンについて、詳しく知りたい方はこちらの記事もお読みください。
マンション購入時の諸費用
中古マンションを購入する際には、物件価格の5~10%程度の諸費用がかかります。
主な諸費用の内訳は以下の通りです。
- 印紙代:売買契約書や住宅ローン契約書を作成する際にかかる税金
- 仲介手数料:不動産会社に支払う手数料
- 保証料:万が一の滞納時に立て替えてくれる保証会社に支払う保証料(返済が免除されるわけではありません。)
- ローン事務手数料:住宅ローンを組む際に金融機関に支払う手数料
- 登記費用:所有権移転登記や抵当権設定登記のために必要な登録免許税と司法書士に支払う手数料
- 火災保険料:火災保険の保険料
- 生命保険料:フラット35を利用する場合に加入する生命保険
住宅ローンをフルローンで利用する場合でも、諸費用は現金で用意することが一般的です。
金融機関によっては諸費用ローンを借りられるケースもありますが、金利も高く、入居時に物件価格以上の負債を抱えてしまうことになるためあまりおすすめはできません。
目安として、物件価格の1割程度の現金を用意しておくことが望ましいでしょう。
購入後にかかる費用
中古マンション購入後にかかる費用としては、以下のようなものがあります。
- リノベーションにかかる工事費
- 引越し代
- 家具・家電の購入費
- 不動産取得税
また、リノベーションをする場合は引き渡し後の工事になるため、工事期間中の住居費と住宅ローンの支払いが同時に発生してしまうことに注意しましょう。
さらに、引き渡し後には月々のランニングコストとして以下のような費用が発生します。
- 住宅ローン
- 管理費・修繕積立金
- 固定資産税・都市計画税
これらの費用は月々の支出となるため、将来的なライフイベントの支出を考慮しながら、事前に無理のない資金計画を立てておくことが重要です。また、修繕積立金は「段階増額方式」を採用しているマンションが多く、経年ごとに増額する計画になっていることも確認しておきましょう。
3.不動産業者をチェック
新築マンションの場合は、建てた会社から直接買うことがほとんどです。なので、不動産業者を選ぶ必要はありません。
一方、中古マンションを購入する際には、不動産会社を選び、その会社を通して購入することが多いです。その場合は、不動産業者選びも重要となります。
良い不動産会社の特徴
- 資金計画に無理がない
- 希望や条件など丁寧にヒアリングしてくれる
- リフォームやリノベーションの相談にも乗ってくれる
- ポジティブなことだけではなく、ネガティブなことも言ってくれる
上記は、「良い不動産会社の特徴」としていますが、同じ会社の中の担当者によっても変わります。合わない担当者になっても、不動産会社自体を諦めるのではなく、担当者を変えてもらうのも検討してみましょう。
4.物件の性能や間取りをチェック

マンションを選ぶ際には、デザインの他に性能や間取り、設備なども大事です。安心で快適な住宅に長く住むためにも、物件の性能や間取りなどをチェックしていきましょう。
物件の希望条件を整理しよう
古マンションを探す際には、まずは自分の希望条件を整理することが重要です。地域、間取り、価格、築年数などの条件をリストアップし、それぞれに優先順位をつけましょう。このステップが明確であればあるほど、後のプロセスがスムーズになります。
次に、不動産のプロに相談しましょう。自分の希望条件に合った物件が市場にあるのか、価格はどのくらいか、資金計画が現実的かどうかを確認します。もし資金計画が厳しい場合は、どの条件を緩和するかを再考する必要があります。例えば、エリアを広げる、築年数を多少古くするなどの調整が必要になります。
また、同居する家族やパートナーがいる場合は、事前にそれぞれの意見をまとめておくことも大切です。家族全員の希望を具体的に整理し、優先順位をつけることで、理想の中古マンションを見つけるための道筋が見えてきます。
新築か中古か
新築マンションと中古マンションにはそれぞれメリットとデメリットがあります。
まずは整理してみましょう。
【新築マンションのメリット】
- 最新のトレンドや技術を取り入れた設備やデザイン。
- 最初の所有者となるため、愛着がわきやすい。
- 定期的なメンテナンスや修繕までの期間が長い。 言ってくれる
【新築マンションのデメリット】
- 一般的に価格が高い。
- 建設中の物件を購入すると、入居までに時間がかかる。
- 未完成物件の場合、実際の日当たりや眺望、管理状態を確認できない。
【中古マンションのメリット】
- 新築と比べて価格が手頃。
- 契約後、住宅ローンの審査が通ればすぐに引き渡しが受けられる。
- 実際の日当たりや眺望、管理状態を確認してから購入できる。
- 特に都市部では、中古マンションの方が利便性の高い場所にあることが多い。
【中古マンションのデメリット】
- 設備や内装が劣化している。
- 定期的なメンテナンスや修繕が比較的早い段階で必要になる。
- 新築と比べて情報が少ない。
新築と中古それぞれのメリット・デメリットを踏まえた上で、あなたの価値観や優先順位に従って選択されるのがよいでしょう。
中古マンションをリノベーションするというアイデアもあります。また、リノベーション済みの物件を購入することで、手間を省き、手軽に快適な住まいを手に入れることもできます。
築年数を検討する
中古マンションを選ぶ際は、築年数、価格、リノベーションの有無、将来の価値の安定性を考慮すると良いでしょう。
一般的に築年数が浅い中古マンションは人気がありますが、価格が高くなる傾向があり、人気エリアでは新築と変わらない価格帯の物件もあります。一方、築年数が経った物件は価格が安く、予算に余裕がない場合には魅力的です。また、建物の評価額は築年数が浅いうちは下落幅が大きくなりますが、築年数が経過すると下落幅が小さくなり、特に築20年以降は緩やかになります。
内装の劣化についてはリノベーションで対処できます。自分好みに一新することで快適な住環境が得られるでしょう。また、リノベーション済みの物件を購入すれば、手間やコストを省け、即入居することもできます。
後述しますが、耐震性を重視するなら、現在の建築基準法に適合した「新耐震基準」の物件が安心です。震度6強〜7程度の揺れでも倒壊しないことが求められており、1995年に発生した阪神・淡路大震災では新耐震基準の建物の7割以上が軽微な被害または無被害で済みました。
内装や間取り、設備を考える
マンションの場合、内装や間取り、設備は物件次第です。まずは居住人数や家族の希望からから必要な部屋数やリビングの広さなどを明確にしておきましょう。
日当たりや眺望、キッチンやバスルームなど設備の条件もあるかもしれません。ただし、地域をある程度絞っている場合、あまり間取りについて細かい条件を決めておくと合致する物件を探すのが難しくなるため、どうしても譲れない優先順位を決めておくことをおすすめします。
中古マンションの場合は、リノベーションを視野に入れることで選択肢が広がります。既存の間取りや内装に不満があっても、自分の好みに合わせて一新することができます。ただし、間取りを変更するような大掛かりなリノベーションには費用がかさむことも。好きな間取りやデザインのイメージを持ちつつ、リノベーションにかけられる予算を明確にしておくと、計画もスムーズに進むでしょう。
耐震基準について
「耐震基準」とは、建築基準法における建物が地震に耐える構造を定めた基準のこと。日本では、過去の大地震のたびに見直されてきました。
中古マンションを購入する際には、この「耐震基準」を確認することが非常に重要です。
計画されている建物が建築基準法に適しているかを行政が審査する仕組みを「建築確認」と言いますが、1981年5月31日までの建築確認で適用されていた基準は「旧耐震基準」、それ以降のものは「新耐震基準」と呼ばれています。
旧耐震基準の建物は震度6〜7の揺れに対応できいないことがあり、1995年に発生した阪神淡路大震災や2024年に発生した能登半島地震でも多数倒壊しています。そのため、金融機関によっては住宅ローンが借りられないことがあります。
なお、1981年以前の建物であっても、管理組合によって耐震補強工事がなされている場合があり、この場合は住宅ローンは問題なく借りられます。
新耐震基準であってもなお耐震基準が気になるという場合は、専門家による建物診断(ホームインスペクション)を受けるのも1つです。
住宅履歴の確認
快適で安全な生活を維持するためには、定期的な修繕やメンテナンスが欠かせません。中古マンションを購入する際には、過去の修繕履歴を確認しましょう。入居後にどの程度のリノベーションが必要か把握しやすくなります。
まず、共用部分の修繕履歴は管理組合に問い合わせれば確認できます。重要事項説明書には長期修繕計画についても記載されるためしっかりチェックしておきましょう。
特に築年数の古い物件で注意したいのが専有部分の給排水管の修繕履歴です。床が綺麗に張り替えられていても、その下の給排水管が交換されていないことがあるのです。給排水管が劣化していれば漏水の原因となり、その修繕費用は所有者が負担することになります。
どこまでリノベーションができるか
分譲マンションにはそれぞれ管理規約があり、リノベーションを行う場合は規約に従う必要があります。
まず、窓や玄関扉、バルコニーは「専用使用権のある共用部分」であり、自己判断でリノベーションできません。また、築年数の古い低層マンションに多い「壁式構造」の場合、室内の壁が撤去できないことが多いので注意しましょう。
物件によっては、騒音問題を考慮して床材のフローリング変更が制限されているケースもあります。
管理規約はマンションごとに異なるため、リノベーションの計画を立てる前にしっかり規約を確認することが重要です。
5.内覧の際のチェックポイント

マンションを選ぶ際には、モデルルームや実際の物件を内覧できることがあります。限られた時間の中で、効率よくチェックするために、事前にチェックリストを作成しておきましょう 。
チェックリストは外観・共用部分と室内に分けておくと良いです。
以下、チェックポイントの例をご紹介します。
【外観・共用部分のチェックポイント例】
- 外壁に目立つヒビはないか
- 階段の手すりやベランダのフェンスは錆びついていないか
- エントランスや共用廊下の掃除は行き届いているか
- ゴミ置き場の衛生状態は悪くないか
- 自転車置き場は整頓されているか
- 管理スタッフの勤務形態
- 掲示板にマナーに関して気になる貼り紙はないか
- 集合ポスト周りにチラシなどが散乱していないか
- 宅配ボックスは総戸数の30%程度あるか
- 総戸数に対してエレベーターの基数が充分か
- オートロックが正常に機能しているか
- 防犯カメラに死角はないか
- 電球が切れている箇所はないか
など
【室内のチェックリスト例】
- 日当たりは良いか
- 開口部からの眺めで気になる点はないか
- 風通しは問題ないか
- 騒音は気にならないか
- 防音性は問題ないか
- 広さや動線に問題はないか
- 収納スペースは充分か
- 給排水の故障はないか
- トイレ、浴室、洗面所の水圧は十分か
- 水回りの位置や大きさをリフォームで変えられるか
- 給湯器は古くないか
- 漏水の履歴はないか
- ベランダに室外機が設置できるか
- 窓サッシはペアガラスか
- コンセントの位置や数は問題ないか
マンションをお得に購入するための制度もチェック
住宅購入は大きな経済効果があるため、政府も国民の住宅取得を後押しする政策を打ち出しています。
ここでは、マンションをお得に購入するために押さえておきたい以下の二つの税制についてご紹介します。
- 住宅ローン控除を利用する
- 贈与税の媒介契約の利用
住宅ローン控除を利用する
住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、国民の住宅取得を後押しする減税政策です。
住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、最大13年間、 各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税額等から控除する制度です。2024年1月から改正され、2025年も同様の基準となっています。
但し、2025年に新築住宅に入居する場合、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン控除を受けるには省エネ基準に適合する必要があります。
中古マンションでも住宅ローン控除を受けることができますが、以下のいずれかで借入限度額と控除期間などの条件が大きく変わりますので注意が必要です。
①省エネ基準に適合するリノベーションなどの増改築を行った買取再販住宅
②省エネ基準を満たさない中古マンション等の既存住宅
加えて子育て世帯などの家族構成でも条件に違いが出るため、詳しくは以下のページで、事前に確認しておきましょう。
参考:住宅ローン減税(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
住宅ローン控除について詳しく知りたい方はこちらも参考にしてください。
https://blog.intellex.co.jp/service/renovexmansion/learnmore/2991.html
尚、この住宅ローン控除に関する政策は、2025年末までの入居者が対象であり、2025年4月時点で2026年以降に関しては未定となっています。
贈与税の非課税枠の利用
住宅は人生の中で最も高額な買い物であり、住宅ローンを利用する場合でも諸費用などまとまった現金が必要になります。若い世代はそうしたまとまった資金を用意することが難しいケースもあるでしょう。
若い世代が父母や祖父母などの直系尊属から、マイホーム取得のための資金(以下「住宅取得等資金」)を贈与された場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度があります。
非課税枠は断熱性や耐震性などの面で「質の高い住宅」と定義される条件をクリアした物件の場合1000万円、それ以外の場合は500万円となります。
参考:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html
マンション購入の流れとポイント

ここまで、マンション選びのために押さえておきたいポイントをいくつかご紹介してきました。
改めて、マンション購入について全体の流れとポイントを確認しておきましょう。
物件探しとその準備
物件探しの初期段階では、まず希望条件と資金計画を整理しましょう。物件購入に当てられる自己資金や月々の返済額、通勤・通学環境などを元にプロに相談しながら進めると安心です。申し込み順に一番手となるため、人気物件などは検討時間が限られることも多くなります。そのため、候補物件が見つかったら優先順位をつけ、迅速かつ柔軟に対応することが大切です。
内覧時のチェックポイントについては第4段落を参照してください。また、現金の持ち出しが必要になるタイミングを確認しておくことも重要です。事前に準備を整え、スムーズな物件購入を目指しましょう。
申込
気に入った物件が見つかったら、売主に「購入申込書」を提出し、最終的な売買価格や引き渡し日、特約などの調整を行います。
新築の場合は、物件に空きがあれば、問題なく申し込みできます。一方、中古マンションの場合は、交渉が先着順となるため、まずは一番手になることが重要です。売主の事情によっては価格交渉が成立しないこともあるため、慎重に進めましょう。
また、申込時に「申込証拠金」の支払いが発生することがあります。相場は1〜10万円ほどで、契約時に手付金に充当されます。なお、売買契約がキャンセルになった場合は返金されます。
申し込みは内覧当日に行うこともあります。中古マンションの場合は、特に迅速な対応が求められるため、いつでも決断できるよう心の準備を整えておきましょう。
契約
価格や引き渡し日などの諸条件に売主買主双方が合意したら、売買契約を締結します。
宅地建物取引業法では、売買契約の前に不動産会社が買主に対して「重要事項説明」を行うことが義務付けられています。ここでは、災害リスクや長期修繕契約、解約の注意事項などが説明されるため、できれば事前に書面に目を通してしっかりと確認しておきましょう。
また、売買契約時には買主は売主に対して「手付金」を現金で支払います。手付金の相場は物件価格の1割程度。契約後〜手付解除期日までにキャンセルする場合は、支払った手付金を放棄しなければなりません。(手付解除期日以降は物件価格の2割の違約金が慣例)
なお、住宅ローンを利用する場合は、審査が通らなかった場合に白紙解約が可能となる「住宅ローン特約」が付帯されているかを必ず確認しておきましょう
引き渡し
マンション購入の最後のステップが「引き渡し」です。売買契約後、買主は契約書面を添付して住宅ローンの申し込みを行い、審査が通過したら晴れて引き渡しが可能になります。
住宅ローンを利用する場合は、金融機関の営業時間内に行う必要があるため、平日の昼間に2〜3時間ほど時間を撮る必要があります。
まず金融機関が買主に住宅ローンを実行し、買主は売買価格から事前に支払った手付金をのぞいた残代金を売主に支払います。同時に、売主はマンションの登記済証(権利証)や鍵、設備関連の書類などを買主に引き渡します。
実務上は司法書士が登記済証を受け取り、法務局で売主の抵当権があればそれを抹消し、次に買主への所有権移転登記と抵当権設定登記を行います。
まとめ
不動産の購入は人生で何度も経験することではないため、一般的に不慣れな方が多いものです。一目で気に入るような物件を見つけるだけでなく、返済も含めたその後の生活が無理なく快適になることを目指しましょう。重要なポイントは信頼できるプロに相談することで、冷静に優先順位を整理することができます。
また、全体的な流れや内覧・契約時の大まかなチェックポイントを押さえておくことで、最終的に納得のいく住まいを見つけることができるでしょう。
リノベーション済みマンションならインテリックスへ
インテリックスのリノヴェックスマンションについて
中古マンションのリノベーションで、業界トップの品質と実績を誇るインテリックスがお届けするリノベーション済マンションが、「リノヴェックスマンション」です。
築年数の経過した中古マンションを一戸単位で取得し、企画設計を行いリノベーションを施した上で、最長20年のアフターサービス保証を付けて販売。
さらにリノヴェックスマンションでは、物件ごとにリノベーション内容を記載した住宅履歴を開示。目に見えない部分についても、独自の検査項目や第三者機関の基準に沿った点検内容をクリアするなど、一定かつ高品質を保っており、快適な暮らしを実現いたします。
実績
2003年10月に商標登録して以来、20年以上に渡りお客様に支持されてきたリノヴェックスマンション。インテリックスが販売してきたリノヴェックスマンションの販売累計戸数は、27,000戸以上、つまり、27,000世帯以上の新しい暮らしを支えてきました。(2024年2月現在)中古マンションを熟知し、数多くのリノベーションを手がけてきたインテリックスだからこそお届けできるのが、リノヴェックスマンションなのです。
品質
インテリックスがこだわるのは、徹底したリノベーション品質です。検査項目は約300ヵ所にものぼり、厳しいチェックをクリアした物件のみを販売。さらに一つひとつの物件は、一般社団法人リノベーション協議会が定める、優良なリノベーションの統一規格「適合リノベーション住宅(R住宅)」に適合しており、発行件数ランキングでも3年連続1位。(2020年~2022年)また住宅履歴のデータ保管も行っており、点検やメンテナンスがしやすくなるのはもちろん、将来売却する際にも役立ちます。
アフターサービス
自社内にアフターサービス専門部署を持つインテリックスでは、業界でも初となる最長20年のアフターサービス保証を実現※1。
給排水管・ガス管・電気等、大切な設備がしっかりと保証されているので、長く安心してお住まいいただけます。実際に住むことで見えてきたお困りごとも、しっかり解決へと導きます。
こうした取り組みの結果、顧客満足度98.7%という数字も達成しました。※2
※1 給排水管を新規交換した場合
※2 2021年10月~2023年2月リノヴェックスマンションご購入者アンケート「アフターサービス保証の満足度」N=416
インテリックスのリノベーション済マンション
インテリックスのリノベーション済マンション

-scaled.jpg)